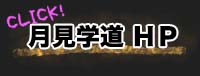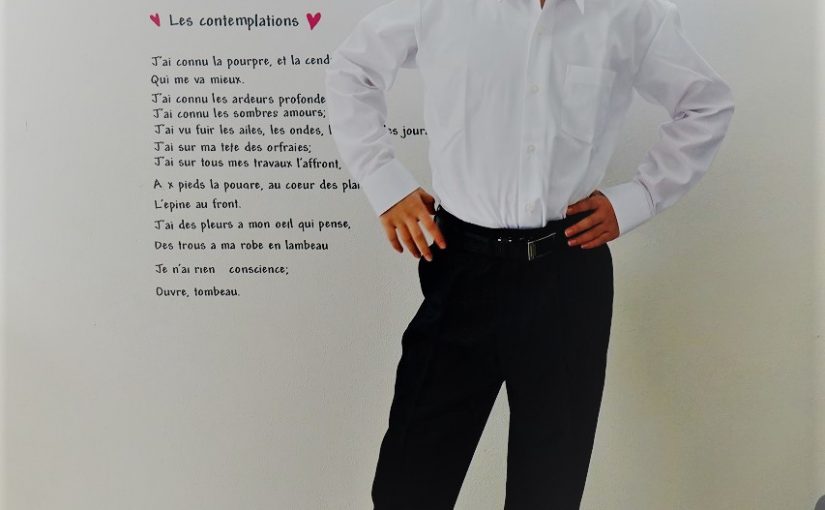進路指導と言うと一般には次の学校に進学する為のアドバイスだと認知されています。
学習塾だってその為の受験テクニックを教えるサービスだと言うのが一般的なイメージです。
私も自分の守備範囲をそこまでにしておけば「学習塾」と言うイメージと仕事内容が一致するので余計な摩擦を起こさずに済むのですがそこは口うるさいオヤジなのでそうはいきません。
どうしても生徒とご家族の将来の幸せについて考えてしまい、ついつい一言多くなります。
例えば中学生が進学する高校を決めた際にどうしてその高校にしたかその後の将来について話そうとします。大抵の中学生はそんな先のことまでは考えていないので答えられません。そこでいろいろな話題を出して刺激を与える訳です。
この時「良い話を聞いた」と、受け取ってくれる生徒は稀でほとんどの生徒は「面倒なこと言って訳分からない」と、思われるのです。
ここが口うるさいオヤジと思われる所以です。
生徒達にとって最も身近な学校の進路指導も次の学校に進学する為のアドバイスなので、もっと先の未来についてのアドバイスなんて受けた経験など無いのですから仕方がありません。
ですがせっかく縁が有って一緒に勉強しているのですから、その生徒達には幸せな人生を歩んでもらいたいといつも思っています。
例を一つ。
生徒には「将来何になりたい?」とは聞かず「将来どこに住みたい?」と、聞きます。
人生100年時代、社会人になっても何度か転職します。住んでいる街にその仕事があれば良いですが無ければ引っ越すか諦めるしかありません。
昭和の様な年功序列、定年まで勤めあげる、役所や大企業なら安心できる時代ではなくなりました。
これからを生きる人達には他人から必要とされる人柄やスキルを持つことが大切です。
だから生徒には「将来何になりたい?」とは聞かず「将来どこに住みたい?」と、聞きます。
きっとこんな切り口の話は他所では聞けないはずなので
「口うるさいオヤジ」と、
思われても続けて行きます。