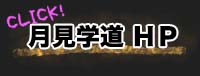吹奏楽部の部長。
中学生の部長「一人」が出来る事なんて大した事はありません。
吹奏楽コンクールで2年連続中学校A編成で釧路代表になった実績を引き継いだのは重い事でした。
先生が転勤のため代わり、
後輩たちをまとめ、
3年生にはリーダーシップを取る様に話し、
でも、自分は病院に通っている。
環境が変わると大人でも大変な事を
「絶対やり遂げなければならない。」
と、思い込み取り組んでいました。
勉強を放って・・・
夏休み中ずっと・・・
成績は落ちました。
当然ですよね。
続きは次号。
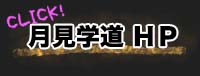
退院後から卒業式直前のバスケットボール大会まで、体育は禁止でした。
たぶんこの成長期に運動が出来なかったから、身長が止まったのだと思います(T_T)
吹奏楽部では部長でしたが、2年生の11月に就任して直ぐ入院。
中学校もちょうど新築中で、完成した部分へと何度も教室を引っ越ししていた時に、
窓から古い市立病院から新しい建物へ引っ越ししているのを眺めていた事もあり、
真新しいその病院に自分が入院するなんて思ってもいませんでした。
釧路市立病院の病室の窓から友達が下校している姿を寂しく見ていると、誰かが必ず遊びに来てくれました。
私の母校東中学校(現幣舞中学校)とは隣同士です。
思い返すと、男女問わずクラスの友達も部活の仲間も全員来てくれたんです。
お見舞いに。
今更ながら幸せな中学校生活を送れたんだなと、ブログを書きながら実感しているところです(^o^)
ここで吹奏楽部の部長だった事がその後の高校受験当日まで大きく影響してきます。
次回中学時代最終回です。
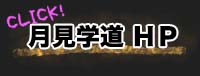
中学時代は色々ありました。
小学生から吹いていたテューバは続けていました。
その様子を見た担任の先生は
「音大に進むなら5教科の勉強よりも、楽器の専門の先生に習う事。」を
勧めて下さいました。
楽器演奏は趣味だと考えていたので、
もしこの時音楽を選んでいたら人生が全然違ったものになっていたでしょう。
私の人生の岐路の一つでした。
※吹奏楽の事については別シリーズでお話しします。
2年生の11月、当時完成したばかりの釧路市立病院に入院しました。
冬休み直前までの約1カ月と、3年生になる春休み中の2週間です。
学校を休んでいた期間の授業のノートは級友が順番に全員で取ってくれたのが一番印象に残っています。今でもありがたい事だったと感謝しています。
遅れた勉強は学校の先生、塾の先生がサポートして下さいました。
この時の経験が学習塾をやってみようと思った大きな要因です。
私の場合は病気で休んだために勉強が遅れましたが、
きちんと学校に通っていても遅れる友達もいます。
遅れている者同志、一緒に勉強して成績を上げていった記憶があります。
縁があって始めた月見学道ですが、
この中学生の時の経験と記憶から、
「生徒さんと、保護者様と一緒に、成績を上げていきたい。」
と、強く思うようになりました。
中学時代はもう少し続きます。
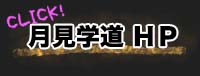
8歳の時に釧路に戻り、
日進小学校(現釧路小学校)に通いました。
ちょうど開校100周年の年で、
記念の年に生徒でいられたのは幸運でした。
この100周年を記念して金管バンドが発足し、
4年生の3学期からテューバを吹き始めました。
きっかけは釧路の港まつりです。
毎年8月に行われるこの祭りの最終日に音楽大パレードがあります。
釧路の夏はジリ(霧雨の激しい感じのもの)がひどく、鬱陶しいものです。
港まつりの土曜日に行われる花火大会が中止になることはしばしばありました。
しかし、日曜日の昼のこのパレードの時間はピーカンになることが多く、
そんな天気の中、駅前から中心街の北大通の6車線もある道路全てを使った行進は圧巻です。
当時の小、中学校のほとんどと、高校全ての吹奏楽部40校以上が参加していました。
カンカン照りの太陽を反射して輝くラッパはキラキラしていて綺麗でした。
道路脇からの声援を浴びている姿は、それは格好良く観え、
自分も演奏者側に行きたいと思ったことを今でも覚えています。
6年生になると学校の金管バンドだけでなく、
釧路の小学生が集まって結成した釧路ジュニアブラスバンドにも参加しました。
当時釧路の教育大学に赴任していた竹内俊一先生(現兵庫教育大学教授)に教えていただいたことは、その後のテューバ人生を考えると貴重な体験でした。
次回は中学時代です。
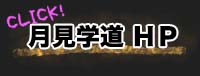
3歳から4年間、阿寒の中徹別に住みました。
この時代については別なテーマで何度もお話しします。
この頃はとにかく楽しかったです。
山が在り川が在り夏は暑く冬は寒い。
周りの山では夏はクワガタ、秋はトンボを捕まえて遊んでいました。
川も傍にありましたが釣りや川遊びはしませんでした。
今は国道240号線沿いの木が全て切られたので、
クワガタは採りにくくなっているかもしれません。
庭の畑にはモンシロチョウやキアゲハが飛び、
裏の畑には秋になるとトウモロコシがたくさん実りました。
街灯などないので夜空は想像を絶する素晴らしさ。
その時住んでいた家には電話がありませんでした。
無くても生活出来た時代だったのですね。
そんなのんびりした日常が懐かしくなる時もあります。
都会型の今の生活と比べれば不便この上ありませんが「生きている」と、言う実感がありました。
ある日、その畑にタンチョウが降りて来ました。
まだ300羽程度しかいなかった時代ですから阿寒でもとても珍しい事でした。
中徹別小学校に入学し、2年生になるときに釧路へ引っ越し。
友達との別れも経験しました。
私の人生観もこの4年間で得たものです。
次回は釧路での小学校時代のお話をします。
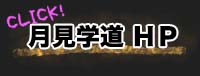
月見学道塾長つきみかずひとのブログ 自己紹介
昭和45年生まれというと、団塊の世代の子供なのでとにかく人数が多いのです。
ちなみに東京農業大学受験時は倍率22.8倍、
釧路湖陵高校は普通科1.4倍、理数科2.6倍です。
今では信じられない倍率ですよね。
私は塾にも予備校にもお世話になっていました。
学歴こそ釧路では名の通った学校を卒業していますが、高校時代は劣等生を経験しています。
授業が分からず置いて行かれていくうちに、どこが分からなくなったのかが分からなくなり、どれを勉強したらいいか分からなくなりました。
だから成績が悪い、点数が伸びない生徒の気持ちも良く判ります。
湖陵に進学したからと言って湖陵で優等生とは限りません。
湖陵で感じる劣等感は中学生のそのものと何ら変わりません。
自己紹介はまだまだ続きます。